うちの子、どうしてこんなにすぐキレるの?
我が子の突然の怒りや暴言に、どう向き合えばいいのか分からない。
幼少期から学童期の子どもが感情を爆発させるとき、つい親も一緒になってイライラしてしまいがちです。
でも、そんな時こそ大切なのは、親が「揺るがない態度」を持つこと。
では、具体的にどうすればいいのか?
- 子供を見守る
- 子供を暖かく包み込む
- 子供に安心感を与える
「見守る」「包み込む」「安心感を与える」──
この3つの姿勢を、一貫して続けることができたとき、子どもの表情や態度が少しずつ変わっていくのを感じます。
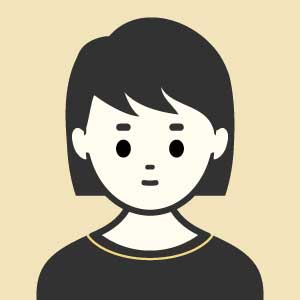
とはいえ、この「一貫して」が、何より難しい。
なぜなら、私がそう感じながら子育てしていたから。
なぜ子供はキレルのか?
幼児〜小学生の子どもがキレるのには、必ず理由があります。
多くの場合、それは自分ではどうにもできないストレスを抱えているから。
大人の目から見ると些細なことも、子どもにとっては深刻で、心の中で処理しきれない感情が積み重なっているのです。
この時期の子どもは、イライラや不安をどう発散すればいいのか、まだ知りません。
その結果として、「キレる」という形で感情を表現してしまうのです。
だからこそ、まずはその気持ちを理解して、優しく包み込むこと。何かを言おうとせず、ただ話を聞いてあげること。
それだけで、子どもは少しずつ安心できるようになります。
でも、子どもがキレたら、優しく包み込むは修行
子どもがキレたときに、優しく包み込み、うまく聞き役になってあげられると、子どもは安心し、落ち着きを取り戻します。
けれど、実際の子育ての中では、そんなふうに冷静に対応できる場面ばかりではありません。
理不尽な言動をぶつけられたり、自分の気持ちに余裕がないときには、心が大きく揺さぶられます。
そんなとき、親に求められるのは、まさに「修行」のような姿勢です。
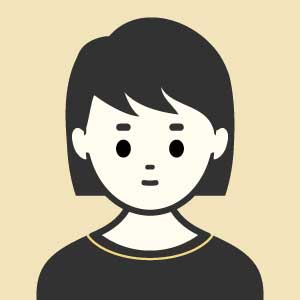
理屈では、わかっていても、理不尽な態度が続く時、エスカレートした時、
私も「一貫して」ということができませんでした。
「親が怒らず見守ることで、子どもがつけあがってしまうのではないか」
そんな思いにとらわれて、つい感情的になり、
キレる我が子を非難したり、悪いことを自覚させようとして謝らせてしまったこともありました。
今振り返ると、自分も未熟だったと強く反省しています。
ごめんなさいと、謝っても、忘れた頃にまたキレる。なぜ?
謝ればいいと思っている子どもたち
なぜ、何度も同じことが起きるのか。
ひとつは、それが子どもというものだから。
そして、もうひとつは、
子どもは、親が謝れと言ったから謝っただけ。謝ればこの場が収まると思ったから謝っただけだから。
このやり取りの中に、親子のすれ違いが生まれています。
だから、何度も同じことが起きるのではないか ──
繰り返し謝らせることで失われるもの
親に言われたから、とりあえず謝る。そんな表面的なやり取りでは、根本的な解決にはつながりません。
むしろ、子どもが自己肯定感を育む大切な時期に、繰り返し謝らせることは、
- 「自分はまたダメなことをした」
- 「親を怒らせる存在なんだ」
と思い込ませてしまっているかもしれません。
自己肯定感が育たないとどうなるか
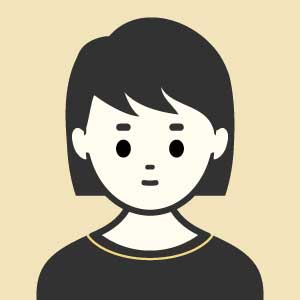
少し話がそれるかもしれませんが、こうしたやり取りの中で、
子どもが自分に価値があるという感覚を持てなくなってしまうことがあります。
何をしても怒られる。どうせまた叱られる。
そんな思いが積み重なると、子どもはやがて自分の気持ちや行動に自信を持てなくなります。
すると、失敗を恐れて挑戦を避けたり、本当の気持ちを隠すようになったり、
時には「どうせ自分なんか…」という諦めの感情に包まれてしまうこともあります。
これは、成長の土台となる「自己肯定感」が育たないことで起こる、大きな弊害です。
本来なら、自分の感情をうまく扱えるようになるための時期に、
「怒られないようにふるまう」「とにかく謝ってやり過ごす」ことばかりを覚えてしまう──
成長の土台となる「自己肯定感」が育たないことを、親はしていないか。
この視点を持つことは、子どもがキレる場面に向き合うときの、大切なヒントにもなります。
「どうすればキレない子に?」から、問いを変える
「どうすればキレない子になるか」ではなく、
「この子は、どんな思いを抱えているのか」──
この問いこそが、関係を変える第一歩です。
子どもがキレる背景には、必ず理由があるのです。
その声なき思いに気づこうとするところから、親子の関係は少しずつ、でも確かに変わっていくと信じてみてください。



